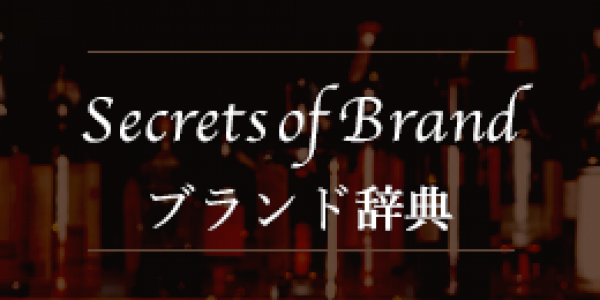PICK UPピックアップ
バーから文化を発信する
「Bartist」という生き方。<前編>
#Pick up
青木”アッシュ”岳明さん
文:Ryoko Kuraishi

生姜もハーブもたっぷり......。アッシュさんが作るカクテルは、出来上がるまでどんな仕上がりになるのか想像もできない。
西麻布の元祖「隠れ家サロン」として、カルト的な人気を誇ったバー「AMRTA(アムリタ)」。
今から20年ほど前、西麻布の路地裏のさらに裏手の地下にひっそりと店を構えた「AMRTA」は、作家、編集者、画家に写真家、哲学者そしてミュージシャンなど、一風変わった趣向を持ち、かつ当時の最先端を走る文化人たちを虜にした。
来日したミック・ジャガーが何度も、お忍びで足を運んだというバーでもある。
その伝説のサロンで「人生最大のカルチャーショックを受けた」というのが、今回ご紹介するバーテンダー、”アッシュ”こと青木岳明さんである。
現在、平日は六本木にある「フランジパニ」(港区六本木6-8-21)で、週末は恵比寿の「MUDAI」(http://www.bar-mudai.jp)、「UNDER BAR」(渋谷区恵比寿西1-3-2)などを中心にゲストバーテンダーを務めている。
車のA級ライセンスを持ち、ドラッグレーサーにして歯学部出身という破天荒な経歴を持つアッシュさん。
異色のバーテンダーとして、西麻布界隈ではよく知られた人物である。
名前の”アッシュ”とは 神宮前にあるバー「HOWL」のオーナーバーテンダー、デニーさんがつけてくれたインディアンネーム、”Asshnka(アシュンカ)”の略だとか。
意味は、遊牧民たちが自らの「パートナー」として慈しむ駿馬の群れの中でも、とりわけ俊足の馬のこと。
自由に生き、気高く走る馬の姿に若き日のアッシュさんの姿が重なる。
それにしても、インディアンネームを持つバーテンダーなんて、日本のどこを探してもお目にかかれないだろう。

「コンペティションには興味がない」というアッシュさんだが、ひょんなことから一度だけ参加したことがある。2006年に開催された「42BELOW COCKTAIL WORLD CUP」では日本代表としてニュージーランドで開催された決勝ラウンドに出場した。
西麻布生まれ、鎌倉育ちのアッシュさんがバーの世界に足を踏み入れたのは、今から20年近く前のこと。
昼間は鳶職や整備士、左官工の仕事をしながら夜はバーテンダーの仕事に打ち込んだ。
熱心に取り組んだ結果20代そこそこで店長まで経験したというから、その「本気度」が伺いしれる。
その後、某大学の歯学部に入学するもバーテンダーの世界の面白さには抗えず、昼間は学生、夜はバーテンダーという二重生活を送っていた。
課題や勉強に追われる歯学部の学生生活は過酷だ。
ほとんど寝ずに平日を過ごすような二重生活を送りながらもバーテンダーの仕事を辞めなかったのは、「バーテンダーという仕事が奥深かったから」と当時を振り返る。
「やるからには常に人より一歩か二歩、突っ込んでいきたいというのが信念です。
上辺だけじゃなくてその世界の奥まで知れば、さらに面白さが増しますから。
真剣度と面白さは比例するんですよね」

ニュージーランドのクイーンズタウンで行われた「42 BELOW COCKTAIL WORLD CUP」決勝大会の模様。シェイク部門で見事優勝!
そうこうするうち、「AMRTA」のバーテンダーとしてカウンターに立つことになった。
歯大生とバーテンダー、二足のわらじだったが、どちらも大切な「わらじ」だった。
そんなアッシュさんに歯科医師への道を捨てさせたのが、「AMRTA」である。
「そうですね。
あそこでの経験がなければ、自分は本当に歯科医師になっていたと思います」
初めてAMRTAのカウンターに立ったとき。
「他のいろいろなバーと比べても、AMRTAは『当たり前』のレベルがものすごく高かった。
たとえばライムにしろ、フレッシュであれば同じ味のものは二つとありませんよね?
だからレシピを決めないんです。
味を決めるのは自分の舌だけ。
僕も師匠に『ジュースは買うものじゃなくて作るもの』と教えこまれましたが、それでもAMRTAのレベルには舌を巻きました。
フレッシュもアイスボールも決して手を抜かず1日に何百杯も作る総ですが、そういうところじゃないんです、AMRITAのすごさは。
例えばあるカクテルをオーダーしたお客さんに『さっきと同じものを』とおかわりを頼まれたら
最初の一杯を作ったバーテンダーが、一杯目と限りなく『同じもの』を作るんです。
そのバーテンダーがホールに出ていたとしても、その一杯だけを作りに戻ってくる。
他のバーテンダーが作ると『同じ』でなくなっちゃうから。
そういうレベルの『当たり前」に衝撃を受けました」
ハイクオリティの仕事をあくまでも「普通に」こなす、そんなバーテンダーの姿にバーテンディングの奥深さ、クリエティヴィティを見いだした。
「考えてみれば、あれが人生で最初のターニングポイントだったのかもしれません」

アッシュさんが主宰したパーティーの一つ。昨秋、表参道の「ル・バロン」で開催したアブサン・パーティ、「Trip the Moulin Rouge ASSH」の告知ポスター。雑誌『DUNE』に掲載されたポートレートを元に製作した。
二つ目のターニングポイントは「AMRTA」の後、白金の「FOB BAR」でのことだった。
当時、カウンターを守っていたのはアッシュさんのほか、「AMRTA」で一緒に働いた双子のバーテンダー。
「AMRTA」から独立して数年、当時はバーテンダー3人でチームを組むことが多かった。
さて、その「FOB BAR」でのこと。
とある晩、カウンターの席でたまたま、日頃から折り合いの悪かったジャズミュージシャンとロックのミュージシャンが隣り合わせになってしまった。
案の定、2人のミュージシャンは声を荒げて口論を始め、ついにはケンカになってしまう。
それでも3人のバーテンダーは2人を放っておいた。
ケンカを終えた2人は、「オレたちはセッションをするからライブのセッティングをしてくれ!」と言ってきた。
数週間後、アッシュさんたちはライブイベントをセッティング。
その晩は他の有名ミュージシャンも加わって、今までに聞いたこともないようなジャンルの、新しいバンドが誕生した。
「その2人はケンカをしたことで意気投合したんですね。
カウンターっていうのは垣根を作らない。
不特定のさまざまなジャンルの人たちが無作為に並ぶんです。
誰もが隣の席に座る可能性があるんです、レストランのテーブルの席のようにセパレートされていないから。
それがバーのカウンターの面白さですよね。
カウンターが、そしてバーが持つ機能や醍醐味を教えてもらった瞬間でした」

ゲストバーテンダーとして都内のとあるパーティーでサーブした、愛知県産パラペーニョを使った「ブラッディ・シーザー」。
「バーとは、文化を生み出し発信する場所。
アーティストとアーティストが出会い、新しい文化が生まれるんだ。
だから、その場所をセッティングするバーテンダーも『アーティスト』なんだよ」
雑誌『ポパイ』や『ブルータス』を手がけた名エディターにして文筆家、森永博志氏に言われた一言である。
この一件と森永さんの言葉に感銘を受けたアッシュさんは自らをバーのアーティスト、「Bartist(バーティスト)」と名乗るようになる。
ただの酒好きの洋酒マニアでも、あれこれ混ぜるのが好きな科学者でもない、「夜の街を彩る文化の担い手」。
「バーティスト」と言う言葉からはそんな自負が見て取れる。
バーテンダーから「バーティスト」へ。
後編では「バーティスト」として腐心する、カクテルメイクの流儀をご紹介しよう。
後編へ続く。