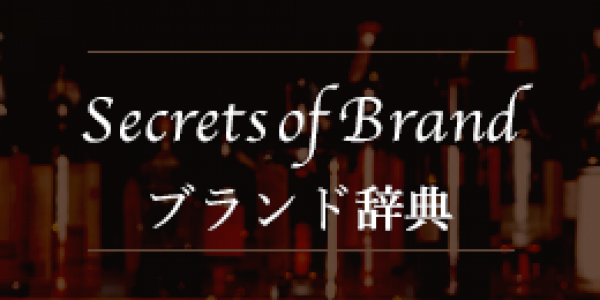PICK UPピックアップ
バーから文化を発信する
「Bartist」という生き方。<後編>
#Pick up
青木”アッシュ”岳明さん
文:Ryoko Kuraishi

浅草の「創吉」で作ってもらった、「ツイスト3.5回転増し&18金メッキ仕上げ」の特製バースプーンを華麗に操る。
バーテンダーはアーティスト。
そんな気づきをもたらしてくれた「AMRTA」、そして「FOB BAR」から独立し、日本で初めて「流れのバーテンダー」となった青木"アッシュ"岳明さん。
バーのプロデュースや立ち上げなどで日本全国のバーに関わり、「日本で最も多くのカウンターに立ち、最も多くの酒屋の見積もりを見てきた」と笑う。
携わってきた数々のバーの中でもとりわけ印象的だったのは、天才肌の料理人、坂井謙介さんと2人で始めた代官山のバー「∞〜BAR EIGHT MAN」。
天井高13m、全70席。
絢爛にしつらえた内装も見ものの、大バコのレストラン&バーだった。
ヘッドバーテンダーとして場を切り盛りすることはもちろん、料理人という異業種の職人とコラボレーションする味わいを知ったという。
知らない世界と密接に関わることで互いに影響を及ぼし合った年月は、彼の価値感やスタイルにも大きな変化をもたらした。
アッシュさんが「食間酒」の存在を意識するようになったのも、こうした料理人との交流に影響を受けたから。
「今の洋酒はワイン以外、食前もしくは食後酒がほとんど。
けれど料理人と数多くの現場でコラボレーションをするようになって、『食事を楽しめる酒』の必要性を痛感するようになりました」
確かに、バーを主体にカクテルを考えるなら食前酒、あるいは食後酒だけでかまわない。
でもカクテルを「火の代わりに水を使って料理したもの」と捉えるアッシュさんは、「バー」という空間の枠を超えて、食と酒を一緒に楽しめる場に思いを馳せる。
「極めたいのは料理と酒の相乗効果。
相乗効果の乗は『×(掛ける)』という意味です。
10+10なら20にしかならないけれど、10×10は100にもなる。
酒と料理、バーテンダーと料理人の相乗効果でどこまでおもしろいことができるのか、求めているのはそれなんです」

こちらがオリジナルの「タイ風モスコミュール」。青唐辛子にライム、タイの生姜、レモングラスにパイマックルーを飾って。
オリジナルのモスコミュールも、そうした思いから生まれたレシピだ。
フレーバーウォッカにカー(タイのショウガ)、ライム、レモングラス、青唐辛子、パイマックルー(こぶみかんの葉)を合わせたモスコミュールは、甘みと酸味、辛みが絶妙なバランスで同居する爽やかな味わい。
タイのホテルにいるかのようなエキゾチックで華やかな香りが漂う。
後味は確かにモスコミュールなのに、不思議に食が進むのは辛みとスパイスの存在感ゆえか。
「カーではなくて高知産の生姜を使い、ジャパニーズ・バージョンにすることも可能です。
その場合は和食に合うフレーバーになる」
あるいは、特製ジントニック(メイン画像参照)。
こちらはジンにローズマリーとスターアニスを漬込むところからスタートする。
おいしさの秘訣は、ローズマリーの香りだけをジンに移すこと。
ハーブの苦みを出さぬよう、ローズマリーを優しく浸すこと、そして引きあげるタイミングに気を配る。
本来は「香りが高くて優しい、まるで女性みたいなジン」と評する、ブドウから作られるジン「ジー・ヴァイン・ジン」を使うが、手に入らないときは代わりにブドウの実を潰して風味をつける。
こちらは中華料理にも合いそうだ。
ここ数年はまっている自家製のスペシャル餃子には、パラペーニョ・フレーバーのウォッカにたまり醤油、西インド諸島マルティニーク島産のシュガーシロップ「トロワ・リヴィエール」を合わせた特製ダレを考案した。
この餃子と特製ダレも、運が良ければどこかのパーティーで味わえるかも。

道具にもこだわる。20年以上使っているバロンのカクテルシェーカーは部分金メッキを施してあるものがお気に入り。こちらも浅草の「創吉」にて。
さて、こうしたレシピの組み立て方はバーテンダーというよりむしろ料理人のスタイルに近い。
実際、料理人やパティシエなど異業種の職人たちに影響を受けることが多いからだ。
もしかしたらオーセンティックなカクテルを求める人には、彼が作るカクテルは刺激が強すぎるかもしれない。
けれど「バーティスト」としてアッシュさんが追い求めるのは、グラスの中に表現できる最高のクリエイティヴィティである。
彼にとってのカクテルとは、メジャーカップを使ってレシピ通りに作るものではない。
なるべく旬の、フレッシュな素材を使って、季節感や時代性をストレートに伝えるもの。
時にはその一杯の中に、真摯なメッセージだってこめられている。
「インスピレーションの源はいろんなところに転がっていて、たとえばナショナルマーケットも想像力を刺激する場所の一つ。
季節によって珍しいフルーツや野菜がいっぱい並んでいて、それを見ると『これとこれを組み合わせたこうなるから、あれを足して…….』なんてレシピのイメージがわき上がってくる。
あの瞬間が楽しいんです」
最近では石垣島出身の料理人、玉代勢文廣さん(「琉球チャイニーズTAMA 」)と「現地特産の『フーチバ』というニガヨモギを使った料理とアブサンで、前代未聞のコラボレーションを」なんて話も出ているし、「世界一おいしい黒毛和牛を知っている」とアッシュさんが絶賛するビーフコンシェルジュの武藤俊一さんとも和牛料理とカクテルのセッションを企画しているとか。

この夏、とあるイベントで提供した特製モヒート。グラスから溢れるほどのミントがポイント。
かつてカウンターを任されていたバーでは常連客に「酒懐石」を披露していたなんて逸話も、料理の世界に精通するバーテンダーならでは。
「懐石は毎月、季節のものを使って『宵の口』から『できあがり』まで、8杯くらいをコース仕立てで提供していました」
日本には四季がある。
美しい季節の移ろいを、ひとつの盆の中で構成されるカクテルの味や香りで表現しようとする試みは、「バーティスト」の面目躍如といったところか。
バーからカルチャーを発信するという「バーティスト」としての活動は、バーカウンターの中にとどまらない。
たとえば、マーティン・スコセッシ監督が制作・総指揮を務めた、ブルース誕生100周年記念映画プロジェクト「ザ・ブルース・ムービー・プロジェクト」の日本先行上映会では、立川直樹氏からの依頼により、ゲストバーテンダーとして700人の招待客に上映作品をテーマにしたオリジナルカクテルをサーブした。
かと思えば、今は亡き名物編集長、林文浩氏(雑誌『DUNE』主宰)が震災後に企画したインスターレション、「JAPAN, THE BEAUTIFUL AND MYSELF〜美しい日本の私〜」展では林氏に乞われ、写真作品を提供したことも。
あるいは、森永博志氏(『原宿ゴールドラッシュ』著者)が綴った、最高の相棒と最高の生き方を手に入れたクリエーターたちのストーリー、『ONE PLUS ONE』(A-Works)にもアッシュさんのインタビューが収録されている。
こうした、独自のバーテンダー哲学を持つアッシュさんのスタイルに魅了され、彼が自らのバーを手がけることを待ち望む人も多いのだが……。
「いまはゲストバーテンダーとしてあちこちを回るスタイルが気に入っています。
もちろん自分のバーをもう一度手がけたい気持ちもあるけれど。
もしそういう機会があったら、バーテンダーがおいしい酒を作って料理人がいて、DJがいい音を流していて、面白いヤツらが世界中から集まってくるような、そんな空間がいいですね。
そう考えると、僕が作りたいのはバーというよりも『サロン』なんでしょう」
そう、AMRTAは確かにサロンだった。
とっておきの遊びを知っている、洗練された大人の心を捉える場所。
新しいことがそこから生まれ、飛び出していきそうな、そんな刺激に満ちた空間。
現代の東京には「バー」はたくさんあるけど、「サロン」が無くなってしまったことを惜しむ全盛期の遊び人は少なくない。
「あそこに行けばなにか面白いことがある、面白いヤツがいる。
そんな文化のるつぼみたいなサロンがあれば、東京はもっと魅力的になる」
かつての遊び人も未来の遊び人も、東京の夜を愛する人々はそんな「サロン」を待ちわびている。