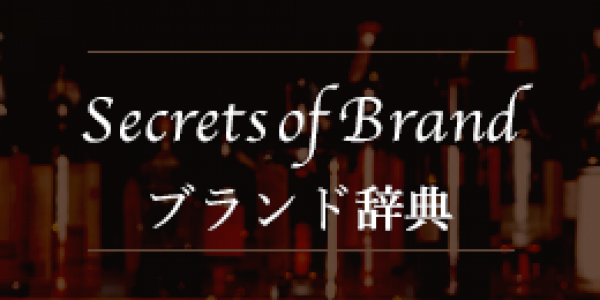SPECIAL FEATURE特別取材
【スペシャルレポート】
薬草酒マニアのバーテンダー鹿山博康氏、
アブサンの故郷、スイス・フランスをゆく。
[vol.02] -
魅惑のアブサン蒸留所めぐり!
<フランス編>
#Special Feature
文:Hiroyasu Kayama

ポンタルリエの目抜き通りにて。
続いて向かったのは、フレンチ・アブサンの都、ポンタルリエ。
フランシュ・コンテ地域圏の中心都市であり、スイスから国境を越えたすぐの街です。
ここは200年前、ペルノの隆盛によりアブサンの街として繁栄を極めました。
今は亡きポンタルリエのペルノ・アブサン蒸留所は、現在チョコレート工場になっています。

エミール・ペルノ蒸留所。
最盛期の20世紀初頭には、大小30のアブサン蒸留所があったそうです。
が、現存するのはたったの2つ。
そのひとつである、日本でもお馴染みのエミール・ペルノ(Emile Pernot)蒸留所を訪れました。
(同じペルノ名義ですが、より有名なペルノはPernod、こちらはPernot)
ここの蒸留機は、スイスで見たものよりひと回り大きいようでした。
スイスは昔ながらの伝統製法を受け継いでいますが、言い方を変えれば大雑把。
一方、フランス側はもう少し規模が大きく、アルコール抽出度数や蒸留液のミドルカットなど、造り方もモダンで緻密に計算されています。
エミール・ペルノが世界的にも良質なアブサンを生産する背景には、現代に見合った緻密な計算や技術があることを納得させられました。
国境を挟んですぐのフランスとスイスですが、アブサンの製造に関しては似ているようでやはり明確な違いが存在しているようです。
これも現地に足を運んでみないと、知り得ないことのひとつでした。

自生するゲンチアナやモミの新芽をゲットする鹿山さん。
ここフランシュ・コンテ地域圏は、アブサンだけではなく、スーズやカンパリのあの苦味の主原料であるゲンチアナ(黄色リンドウ)の産地でもあります。
(国境を越えたスイスのヴァル・ド・トラヴェールの高山地帯も同様)
ゲンチアナはリンドウ科の植物の一種。
学名はGentiana Luteaで、ちょうど我々が訪れた夏に、黄色い花を咲かせます。
という訳で、近所の農夫さんに許可を得、シャベルと軍手を近所のスーパーで買ってきて採掘をしてみました。
ちなみに、この地域のアブサン蒸留所はアブサンを造る傍ら、ゲンチアナリキュールやゲンチアナのオードヴィーも手がけています。
ゲンチアナは「高山地帯の水はけの良い斜面の中腹」という環境が揃えば、至るところに自生しています。
自然薯のように根が深く、キレイに掘り起こすのは至難の業。
そのため、伝統的に“悪魔のフォーク”と呼ばれる、ゲンチアナ専用の採掘道具もあるほどです。
さすがはシーズン最盛期ということもあり、たっぷりと採取できました。
付け加えておくと、このあたりは、モミの新芽のリキュール「サパンリキュール」の産地でもあります。
高山地帯には多くのモミの木が自生していたので、こちらももちろんゲットしました。

ビアン・レ・ズュジエ村の共同蒸留所。
さて、エミール・ペルノ蒸留所のスタッフの方に面白い場所に連れてってあげると言われ案内してもらったのが、ビアン・レ・ズュジエという村。
アブサンの都、ポンタルリエから車で30分ほど行ったところにある、人口500人にも満たない小さな集落です。
ここに、フランスでも数が少なくなっているという、誰もが使える共同蒸留所があるのです。
(共同井戸ならぬ、共同蒸留所です!)
19世紀後期に設置されたビアン・レ・ズュジエにある共同蒸留施設は、役所にこの日に蒸留すると伝えれば、建物に入る鍵をもらえて自由に蒸溜できるという仕組み。
今でも近隣のおじいさんが数人で、自分たちの敷地内で採れたフルーツを原料に、自家発酵・蒸留を経て、自家製フルーツブランデーを造っています。
あるいは、アブサンやゲンチアナのオードヴィーを個人蒸留している方もいます。
フランスでは、商用目的以外の個人蒸留は200ℓまで許可されています。
案内してくれた人に聞いたところ、申告制ではあるものの申告はあくまで緩やかで、役所の人も昔からある伝統的なことだからとある程度黙認しているとのこと。
ちょっと前の日本の、各家庭における梅酒と共通するものがあるようです。

現在、この共同蒸留所を利用するのは一部の老人くらいとのことでしたが、ほんの30年、40年前までは近隣の主婦や若い方たちも当たり前のように利用し、ここで井戸端会議が行われ、集落に欠かせないコミュニティの場として機能していたそうです。
(蒸留には水が必要なので、すぐ隣に水場もあり、洗濯もできる!)
しかしこのような共同蒸留施設は1914年に第一次世界大戦勃発してから、ほとんどが姿を消してしまいます。
軍が蒸留機を武器としてリサイクルするために持ち去ってしまったのです。
(日本でも戦時中、寺社の鐘が武器としてリサイクルされたのと同様です)
また戦争による「贅沢は敵という風潮」、のちにアメリカで禁酒法が施行されたことによる「酒は悪という風潮」がこれを後押ししました。
そんななか、ビアン・レ・ズュジエの集落では、住民がコミュニティの場として共同蒸留所を守り抜いたおかげで、こうして現存することになったという訳です。
蒸留機は100年も前のもので、組み立て式。
火元は直火の薪というシンプルでプリミティブな構造です。
フランスの片田舎にいまだに生きる蒸溜の伝統・文化を、身をもって感じることができました。